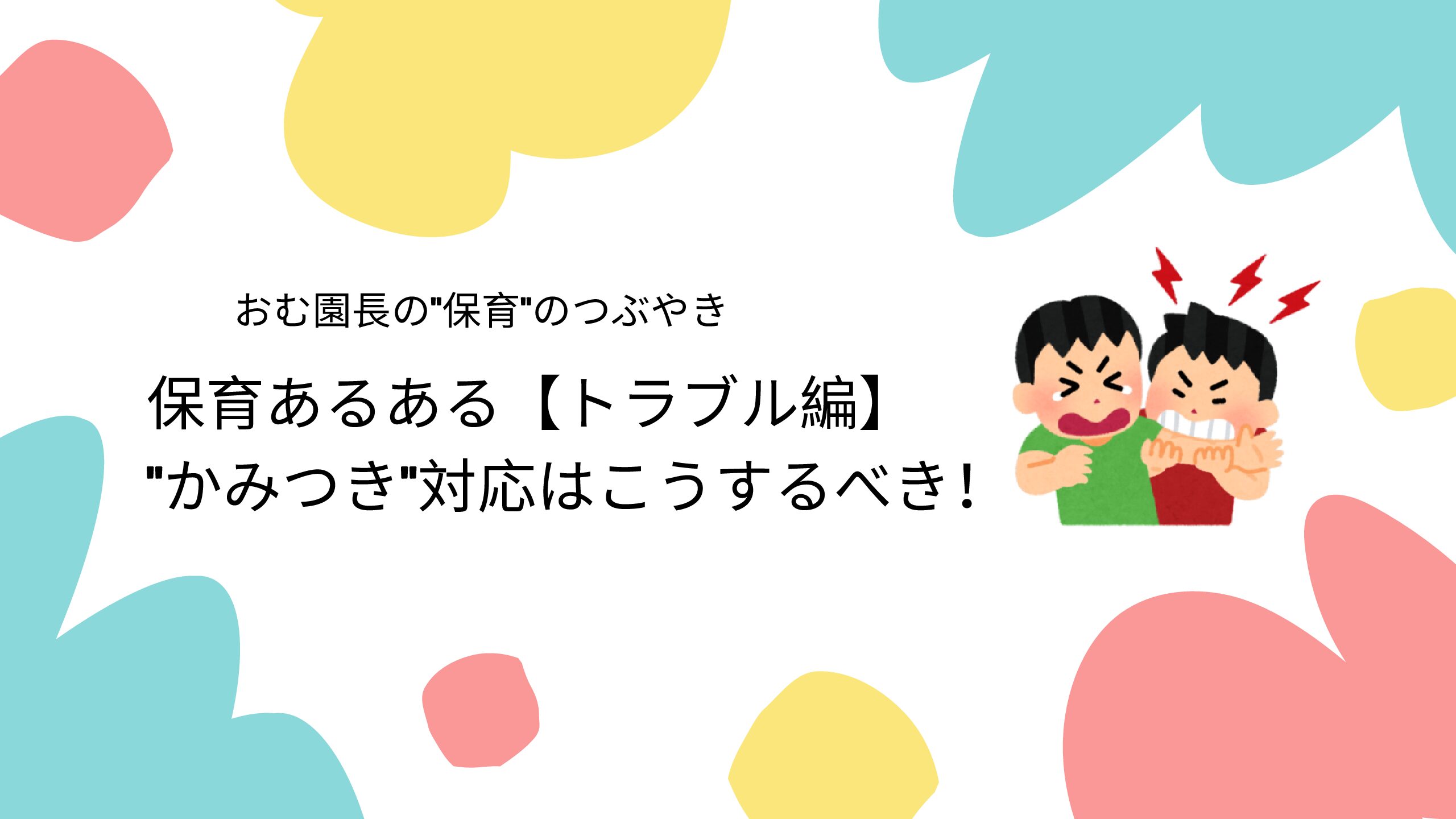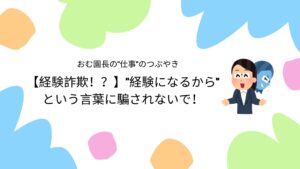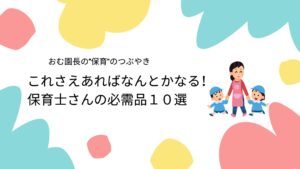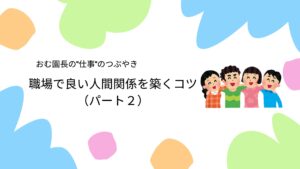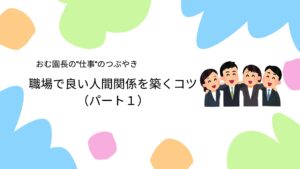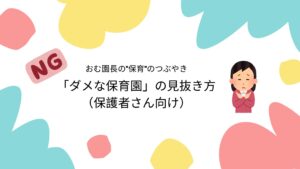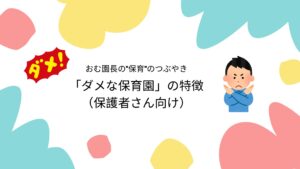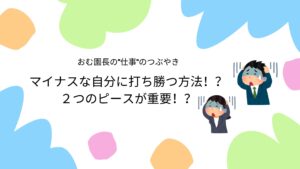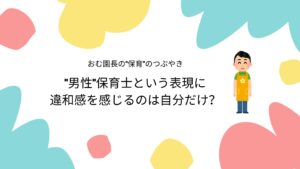色んなことを発信していくつもりなので、こういう”あるある”も打ち出していこうかと思います(´▽`)
管理者目線になってしまうのですが💦 最後まで読んでいただけたら幸いです☆
まず、私の”かみつき”体験談にお付き合いください(´▽`)
保育園で過ごしていると、いろんな問題がありますよね~💦
トラブルで代表的なのが「かみつき」
主に1歳から2歳くらいの年齢のお子さんに多いかと思いますが、ここで私が言いたいのは、”噛んだ子がいけない”とか”保護者さんの愛情が足りないからこんなことが起きるんだ”とか、そういうことではなく、言いたいのは「園内で起こった”かみつき”行為は、防げなかった園側の責任」だということです。
20年保育士をやっていく中で、いろいろな園のやり方を見てきましたが、一番驚きだったのが「噛んだお子さんの保護者さんから、噛まれたお子さんの保護者さんへ謝ってください」という園側の対応でした。
さすがにあの時は、当時の園長に「その対応はありえない」と反論しました( ;∀;)
結果的にさらに反論されましたが(笑)
かみつきって、とてもデリケートな問題なので慎重に対応しないといけないのですが、
当時の園長は「園側がいけないのではなく、噛んだ子どもがいけない、噛んだ子の保護者がいけない」と判断したんですよね。園内で起きたこと、園でのお預かりの時間に起きたトラブルは園側の責任です。
保育園でも児童館でも放課後等デイサービスでも、お子さんが関わる事業は何でもそうですが、トラブルが起きてしまった時、保護者さんが一番気にしていること、見ているところは、きっと“施設側の対応の仕方”だと私は思います。
決して謝罪をすればいいという問題ではありません。
お子さんの怪我の度合い、噛んだ子と噛まれた子の情緒面、お互いの保護者さんの気持ち・・
大事なのは”子ども”や”保護者”の気持ちにいかに寄り添うかです。
前置きが長くなりましたが💦 ここで“かみつきが起きた場合の対応の仕方”をお伝えします。
あくまでも私の考えですが、少しでも参考になれば幸いです。
まず!園で子ども同士のかみつきが起きた際、関わる人物は、噛みついてしまった子、噛みつかれた子、両方のご家庭、そして保育者となります。(今回はあくまでも”かみつき”の案件で説明します)
ここで重要なのは、それぞれのフォローの仕方ですよね。
まず、噛まれた子やそのご家庭の保護者さんへの対応だけを考えるのは×。
噛んだ子とそのご家庭のフォローも、同じように親身になって対応すると〇。
そして、、、ここが私にとっては重要ポイント。
保育士さん(担任やその場にいた先生)たちのフォローができていれば◎。
ここで、それぞれの立場の対応の仕方を説明します。
【噛まれた子への対応】
① すぐに噛まれた部分を処置する
まず、傷の確認と手当てをしましょう。軽い場合はとにかく冷やし、ひどい場合は医療機関へ相談したり、必要に応じて病院へ連れて行くなどの対応を行います。(保護者への連絡を忘れずに)
※噛まれた部分を水や保冷剤などで冷やす際、昔はその部分を”揉む”というやり方がありましたが、今はNG行為なのでご注意ください💦(噛まれた部分を揉むことで、毛細血管がさらに傷つき、内出血が広がったり、腫れが悪化したりする可能性があります。特に、乳児や幼児の皮膚は薄くデリケートなので、強い刺激を加えるのはよくありません。)
② 噛まれた子の気持ちのケアを絶対に忘れずに💦
「びっくりしたね、痛かったね」と言葉をかけながら、しっかりその子に寄り添いましょう。噛まれたことがトラウマにならないように、その後の園生活を安心して過ごせるよう配慮することが大切です。
【噛まれたご家庭への対応】
※ここで説明する内容は“帰りのお迎え時”の場合です。
① かみつきが起きた状況をしっかり説明し、謝罪をする
事実をしっかり伝えましょう。玩具の取り合いだったのか、咄嗟に起きた出来事だったのか、その時の状況を伝えることで、保護者さんの受け取り方も大きく変わります。ここで大事なのは“噛んでしまった子”が悪者にならないように慎重に説明することです。
② かみつき後に保育士が行った対応を説明する
どんな処置をしたのか、噛んだ子とのその後の関わりはどうだったのか、園の対応がその時の最善を尽くしているのか、それによって保護者さんの受け取る気持ちは大きく変わります。
③ 噛まれた後のお子さんの様子を伝える
噛まれたその時だけでなく、保護者がお迎えに来るまでの間の様子を伝えること。(痛がっていたのか、気にしている様子はなかったのか、噛まれた痕や赤みはどのくらいなのか、冷やしたのか、落ち着いて過ごせたのか など)
④ 今後の対策を説明する
「今後は気を付けて見ていきます」は誰でも言えます。重要なのは、具体的な対策を伝えることです。例えば、遊んでいる時は必ず保育士がその子の間に入る、環境設定を変えるなど。正直”かみつき”が起きた当日に急に対策を練るのは難しい場合もありますね。かみつき後の保育はその後も続きますし、お昼寝中は連絡帳等の業務に追われますし💦
ポイントは“説明の仕方”です!
「気を付けて見ていきます」ではなく、
「今回はみんなで動こうとする際に起きてしまったので、移動の仕方や保育者の配置など、そのような部分に気を付けていきながら今後対策をしていきます。」
(あくまでも簡単な例ですが)
「どうやって移動する?」「保育者はどこに配置する?」など、細かな情報まで伝える必要はありません。その部分は保育士さん同士で決めれば大丈夫です!
大切なのは「しっかり考えています」という姿勢を見せることです(´▽`)
※経験上、活動の切り替わりの時間帯が一番トラブルが起きやすいです!!
(活動前のトイレへ行く時間帯、活動後の片付けの時間帯、給食後の片付けの時間帯、お昼寝前のトイレの時間帯 など)
⑤ 説明の終わりにもう一度謝罪をする
しつこく謝り過ぎてもNG。誠意は謝罪の言葉ではなく、問題に対する園側の姿勢です。謝罪の言葉は2回でいいと思います。
- 最初のお迎え時の謝罪
- 説明終了後の謝罪
保護者さんが一番求めているのは、
「できれば同じようなことが起きないでほしい」
「自分の子も相手の子も楽しい園生活を過ごしてほしい」
ということだと思います。
⑥ 次の日に登園した際、昨日の降園後のお子さんの様子を聞く
「昨日は申し訳ございませんでした」の一言だけで、何事もなかったかのように話を進めるのは×。
謝罪もないのは問題外ですが……
私が思う一番ベストな会話のやりとりをお伝えします♪
 保育士
保育士○○くんおはよう~!お母さんおはようございます



※保育士にかけ寄ってくる



おはようございます



昨日は大変申し訳ございませんでした💦
○○君、お家に帰ってからどうでしたか?😟💦
痛みや痕はどうですか?



大丈夫ですよ~あんまり気にしている様子なかったですし、痕も引いてきました。



そうなんですね💦お家で気にせず過ごせていたならホント良かったです💦
引き続き怪我の具合やお友達との様子を見ていきますね。



よろしくお願いします



〇〇くん、お友達がみんな集まるまで○○して遊ぼうか??♪



※母から離れて、好きな遊びに取り掛かる



じゃあママにバイバイしようか、ママいってらっしゃ~い



バイバイ~☆



いってきます
以上、簡単ではありますが、私が思うベストなやりとりです。
上記のやりとりは、保護者さんへの謝罪だけでなく、噛まれた子の様子や怪我の具合を気にかけながら、今日も一日楽しく過ごせるようにという配慮がなされています。
あくまでも、“かみつき”が軽度の場合の対応になります。
“かみつき”は続くときは続きます。ましてや、同じ相手に何度も続くこともあります。歯形がくっきりつき、出血するパターンもあります。
“かみつき”の度合いによって対応方法は異なりますので、発生した場合はまず一人で考えず、先輩や主任、園長に相談しましょう。決して一人で背負う必要はありませんからね。
【噛んだ子への対応】
まず、噛んだ子には決して頭ごなしに怒ってはいけません。
「なんでしたの!だめ!痛いでしょ!」と子どもに威圧的な態度を取ってはいけません。
噛んだ子の気持ちも受け入れつつ、噛まれた子の気持ちを落ち着いて代弁することが大切です。
これは子どもの世界だけでなく、大人の世界でも同じです。
例えば、間違いをした、失敗をした、そもそもそうなった背景にはいろんな理由があると思います。
ただ頭ごなしに怒られただけでは「怒られた」という印象だけで「え、なんで怒られたんだろう?理由があったのに、そんなに怒られなきゃいけなかったの?」と疑問が残ることがありますよね。
いろいろすり合わせていくと、噛んでしまった子がなぜその行動を取ったのかが見えてくることがあります。
しっかりと見極めましょう。
【噛んだ子の保護者への対応】
一概には言えませんが、私個人の考えでは1回目の軽度の「かみつき」(痕が残らない、少し赤みがある程度)の場合は、噛んだ子の保護者に伝える必要はないと思っています。
ここで重要なのは“保育士同士で共有し、様子を見守ること”です。それが大切だと思います。
そして、もし2回目、3回目と続いた場合には伝える必要があると思います。
ただし、その際には「噛みつき=悪いこと」として説明するのではなく「友だちとの関わりの中で、興味や感情の表現として噛んでしまうことがあります」といった、あくまでマイナスな伝え方をしないことが重要です。
ここで大切なのは“噛んでしまった子の園での様子とご家庭での様子を日々伝え合い、共有していくこと”です。
お子さんも保護者さんも安心して過ごせる体制を整えていきましょう。
【保育士さんのフォロー】
何かのトラブル対応時に園側の対応として、やってはいけないことは”不安になっている保育士さんをそのままにしておくこと”だと思います。保護者対応をどうしたらいいか分からない時は、先輩保育士や主任、園長に相談しましょう。冒頭でもお伝えしましたが、“かみつき”はデリケートな問題です。だからこそ、担任の先生が一人で抱える必要はないと思います。もちろん、初めから主任や園長が出るべきではない、担任だから自分で言うのが当たり前だという考えもあると思いますが…。
何事も経験だと思って対応させることはNGです。もしそうするのであれば、対応の仕方を教えてから、実際に保護者さんの前で説明や謝罪をする場合、見守ってあげるべきだと思います。
その時、保護者対応が的確でなくても、フォローに入ってあげればいいだけです。失敗を経て成長するのはもちろん大切ですが、それが丸投げであれば保育士さんのトラウマになってしまいます。
あとは、間違いや失敗があっても絶対にその保育士さんを責めないことが重要です。
今回は大分長々の説明になってしまいました・・・これ観ている側の気持ちに経ってないような・・・( ;∀;)
ちょっと事細かく説明しすぎましたが💦どこか一部分でも参考にしてもらえたら、ただただ嬉しいです💦( ;∀;)
以上、保育あるある【トラブル編】”かみつき”対応はこうするべき!でした☆
何事もそうですが、
まずはトラブルが起きたとしても一呼吸おいて、落ち着いて行動することを心がけしましょう☆⤴(*´▽`*)
本当に最後まで読んでいただき有難うございました💦